
自分だけの「トキワ荘」を探せ!川村元気&香田哲朗
2021.03.29
映画『告白』『モテキ』、そして社会現象を引き起こした『君の名は。』など、数々の大ヒット映画のプロデューサーを務め、小説家、脚本家、映画監督などジャンルを越え幅広い活躍を見せる川村元気さん。
川村さんは著書『仕事。』の中で、世界をおもしろくしてきた先輩たちの話から「人生を楽しくする仕事のヒント」を紹介しています。そんな川村さんに、ご自身の「仕事のヒント」を聴きました。
「成功したら別ジャンル」で武器を増やす20~30代
 香田さん
香田さんまずは我々が学生の頃からこれまで何をやってきたかを話していきましょうか。
 川村さん
川村さん僕は大学生の時就職活動をして、エンターテインメント系の数社から内定をもらったのですが、自分が好きなのが映像と音楽と物語で、これらをすべて内包するのが映画だったので、東宝に入社することを決めて新卒として働きました。
最初の2年間は大阪の映画館でチケットのもぎりをやっていました。『千と千尋の神隠し』が公開された時「映画館ってこんなに人が来るのか」と思ったら、日本トップの興行だったというのが後でわかって。3年目で企画のセクションに移り、26歳の時に『電車男』で映画を作りプロデューサーとしてデビューし、そこからいろいろな作品を作りました。今41歳なので、映画を作り始めて15年ぐらいですかね。この間、数えたら作った映画が40本超えていました。

映画『告白』『モテキ』『君の名は。』など数々の大ヒット映画のプロデューサーを務め、小説家、脚本家、映画監督などジャンルを越え幅広い活躍をされている川村元気さん。
 香田さん
香田さんすごい!小説を書いたのは何歳の時ですか?
 川村さん
川村さん32歳の時ですね。映画は『電車男』から始まって、31、2歳ぐらいで『告白』や『モテキ』などを作り、やや燃え尽きた感じもあり、何か新しいことをやらないとマンネリ化してパターンにはまっちゃうなと思ったんです。それで、自分でオリジナルストーリーを書いてみようと思って取り組んだ小説が『世界から猫が消えたなら』です。
30代になってから小説を書いたりアニメーションの仕事をやるようになり、最初の大きなアニメーション映画が『おおかみこどもの雨と雪』なんですが、実写の経験がアニメでも通用するかと思ったら一から勉強し直しでした。アニメの世界では考え方が違ったり、観る人の求めるものが違ったから。そうやって小説、アニメ、音楽の仕事とちょっとずつ仕事の種類を変えながらやっていって、『バクマン。』でサカナクション、『君の名は。』でRADWIMPSと一緒に映画音楽を作ったりするところにつながっていきました。
ジャンルの場所を変えながら新しいことをやっていった結果、映画に戻ったときに自分の武器が増えていた、という感じがあります。
 香田さん
香田さん川村さんのお話を聞いていると、「肩の力が抜けている戦略家」という感じがしますよね。ちょっと前だと、みなビジネスの成功を目指し頑張っている「意識高い系」と言われた人も多かったですけど。就活の時に思い描いていたことは、当時想定していたよりも実現できている感じですか?
 川村さん
川村さん今振り返ると就活していた頃って、全然何もわかってなかったと思うんですよ。それは当たり前で、20代前半でやりたいことが定まっている人なんてそんなにいないわけです。
僕も何をやりたいか自分でよくわかんなかったから、色々な場所に行って「こういうことをやったほうがいいよ」と教えてもらうようなことが多かったし、あまり「自分はこれがやりたいんだ」「これをやんなきゃダメなんだ」と縛られてはこなかった。いい意味で、人に言われたことをやってみたり、気付かされるということに幅広く対応してきたという感じが強いかもしれないですね。
新人時代、映画館での下積みで鍛えていたこと
 香田さん
香田さんちなみに、新人の頃に映画館でチケットのもぎりをされたいたということですが、その経験はその後にどういう影響を与えましたか?
 川村さん
川村さん映画館でチケットを売って観てもらっているという当たり前のことがわかったということですよね。毎日、映画館で1,000円、2,000円払っているお客さんのお金が集められて映画が作られている。作っている側にいると、お金の流れがわからなかったりする。映画館にお客さんが入らないと悲惨だし、入っているとすごく楽しいのが映画なんだなと気づけたことは大きかったです。映画というのはどこまでいっても興行なんだなというのは身に沁みましたね。
もう1つは、コツコツ自分の企画を考える時期でもあったということですね。20代前半ってすぐに成果を求められず、2年ぐらいは育成期間みたいなところもあるので、その時間を使っていろいろな企画を考えていました。
 野澤
野澤川村さんはご自身で会社を経営されていますが、作品もずっと作り続けてきていますよね。作品を作るという仕事の道を決めたのはいつ頃ですか?

アカツキ会社説明会「ACE」では学生からの質問を常時受け付けながらインタラクティブに進行する。進行役はアカツキ初の20代執行役員で、物語と体験をつくる「コンテンツ(IP)プロデュース」事業をリードする野澤。
 川村さん
川村さんいろいろなことをやっているようで、僕の仕事は一貫して“ストーリーテリング”だと思います。映画、小説、アニメ、音楽、広告、すべてにおいて、今は物語がすごく大事な時代。その物語を考えるのが好きで、自分は物語を色々な場所で表現しているんだなと気づいてからは「ストーリーテラーで仕事をしていく」と決めたんです。
反対に頑張っても上手くできないこと、あまり得意じゃないことは頑張りすぎない。それを助けてくれる人たちと組もうと思ったんです。小説だったら編集者、映画だったら現場をまとめてくれるプロデューサー、映画や小説を大きくしてくれる宣伝マンみたいな人たちは大切なパートナーです。
映画会社で企画やりたい人は多いんですが、みんなが企画が得意なわけではない。自分が得意だと思いこんでいることの横や反対側に、実はもっと得意なものがあるかもしれない。それに早い段階で気づいた人が強いと思います。
エンジニアから経営者へ。仕組み作りも”ものづくり”
 香田さん
香田さんよく単体のスキルが才能のように言われますが、仕事はもっと複合的で、チームの関わりの中で評価されていくものです。だから、自分のプレースタイルに気づくこと、どんな環境に身をおけばパフォーマンスが上がるかに気づくことが大事ですね。
 野澤
野澤香田さんはエンジニアから始まって、エンターテイメントの業界で経営という方に進まれています。これはどういうキャリアストーリーがあったのですか。
 香田さん
香田さん僕は川村さんのように自分で物語を作りたい、キャラクターを作りたいというよりも、もっとミーハー的にエンタメが好きで、その中で自分が得意だったのがエンジニアリングだったからゲームという分野に入っていったんです。
だけどゲームだけでなく、音楽、アニメ、漫画も好きだし、それを仕事としていく過程で結果的に経営や事業を作ることになっていったんです。人より横断的なところが得意なんです。

アカツキ代表取締役CEO香田哲朗。創業期からエンジニア兼ディレクターとしてモバイルゲームの開発、COOとしてアカツキの組織と事業づくりを担う。現在はIPプロデュース事業を中心に第二創業期のアカツキを牽引するだけでなく、意欲的なアーティストを支援する一般財団法人東京アートアクセラレーションの理事も務める。
 野澤
野澤香田さんの“ものづくり”は、やりたいことが得意なパートナーを連れてきて、香田さん自身は仕組みを作っているなという感じがします。会社と会社はどう組むとうまくいくか、お金の流れはどうするか。その仕組みを作ることも、“ものづくり”と言えるかもしれませんね。
頼み頼まれる関係の中で「やりたいこと」を育て、強い企画にする
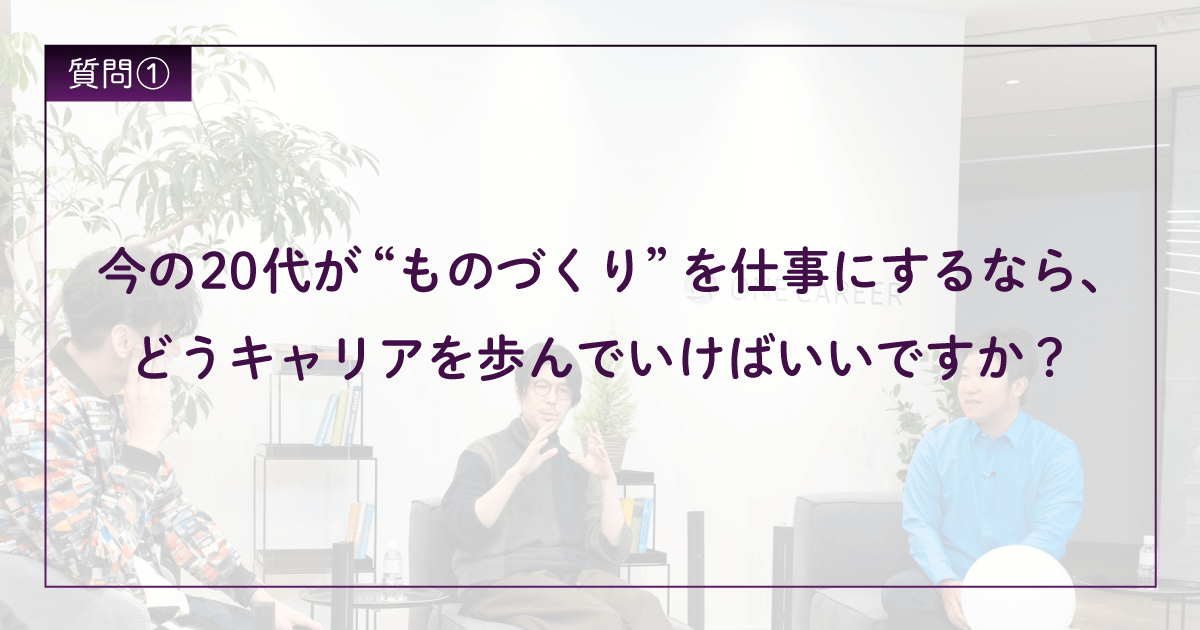
 野澤
野澤ここで1つ目の質問ですが、お二人が若かった頃と比較して、今の若い人たちがものづくりを職業にするとしたら、どうキャリアを歩めばいいですか?
 香田さん
香田さん川村さんのチケットのもぎりの話を聞いていて思うんですけど、あえて一般的には地味でわかりやすい派手さがないことでも、人のニーズに応えていくっていうのが、仕事の基本だと思います。今の時代、自分一人で何か作ろうとしたらカジュアルに作れる時代だから、人に頼まれたことをすることが無駄に思えるかもしれないけど、個人・組織関わらず大事なことは人に頼まれたことで学ぶことが多いですから。
 野澤
野澤川村さんはどうですか。
 川村さん
川村さん今はおもしろい子がインターネットにいっぱいいますよね。僕はEveというアーティストと仕事をしているんですが、彼は自分で映像やアニメーションのアーティストをどんどん見つけてきて、SNSで繋がり、自分がおもしろいと思う人と作品を作っている。会社がやっていたことを個人でできる時代になっていて、その流れは間違いなく加速していくでしょう。
一方で、自分のやりたいことだけをやっている人たちは、そう多くないんです。若手から相談されるとき、「じゃあ、やりたいことを教えてよ」と質問するんですけど、やりたいことは1個目、2個目、3個目までは出るけど、4個目ぐらいから出てこなかったりする。
僕もそうですが、実はそんなにやりたいことって、数多くはないんです。数えても3個ぐらいだったりする。それに企画って、その3個を全部まとめて練り上げて、やっと世間に出せるような強いものになるんです。だから、20代は組織やチームの中で個人の力を蓄えながら、誰と組んで、どう企画を作っていくかを試して行った方がいいと思います。
自分を鍛え上げる「トキワ荘」を探せ
 香田さん
香田さん今はスマホで無限に情報にアクセスできる時代だけど、20代は選ぶための経験値が少ないわけだから、選択が難しいですよね。
 川村さん
川村さんやれることがありすぎる時代だから、やらないことを決めることが大事。そう発想を切り替えていくことで、見えてくるものがある。やらないことを決めるっていうのは、実は企画を作る際も同じなんですよ。
これだけインターネットで作品が発表できる時代なのに、最近のヒット作品はやっぱり『ジャンプ』から生まれているっていうところもおもしろいですよね。毎週アンケートで順位がつく『ジャンプ』で作品を発表しつづけるというのは、ものすごく大変なことだと思います。でも、どこか突き抜けるには、ある程度プレッシャーが必要だってことかもしれないですよね。
 香田さん
香田さん昔からすごい確率ですごい人を輩出する場ってありますよね、松下村塾とか。現代でも強い会社、強い学校とかはある。そういうすごい人を出す場の独特の空気感っていうのは絶対あると思うんですよね。

 川村さん
川村さんエンターテインメントでいったらトキワ荘ですよね。現代だと『ジャンプ』もそうだし、僕が作ったSTORYという会社もそうなってきている。どの分野でもトキワ荘みたいな場をどう作れるかということが大事。
一方でどうしても、似た価値観の仲間や、同世代だけで固まりがちなのも問題で。だから、普段話さないような世代の人や、他のジャンルと人と話すことも大事なことだと思います。
20代は自分にとってのトキワ荘を、おもしろがりながらつくることが大事ですね。それに、トキワ荘の中でも、それぞれ得意技が違ったりします。自分が得意だと思うことをやってみて、うまくいかなかったらちょっとずらしてみる、を繰り返していくうちに、トキワ荘の中での自分の居場所ができると思います。
※トキワ荘:手塚治虫をはじめ昭和を代表するマンガ家たちが住み、切磋琢磨しながら青春を過ごした伝説のアパート。
嫉妬は「する側」ではなく「される側」でいる。そのために膨大な過去に学ぶ
 野澤
野澤参加者から川村さんにこんな質問が来ています。
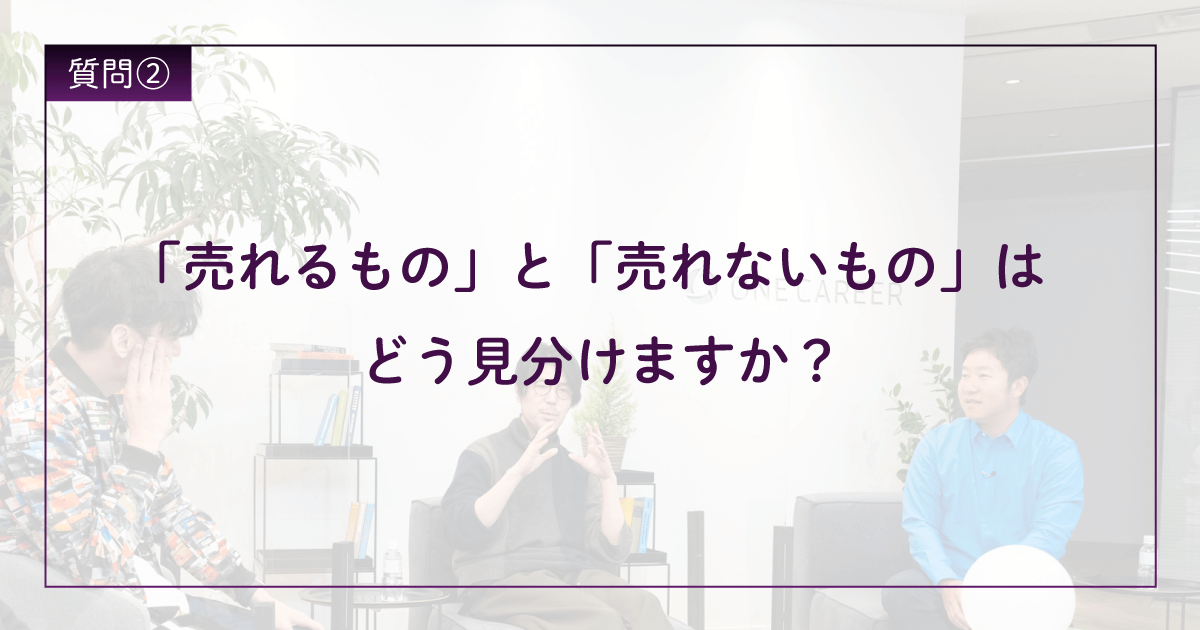
 川村さん
川村さん売れるものがわかる魔法があるなら、みんな欲しいですよね。それができないから、自分が好きだと思うものを信じてやるしかないんですよ。本当に自分が好きなものから始めるんだけど、好きなものが本当におもしろいかどうかは、色々な人と作ったり、叩かれたりしながら精度が上がっていくわけです。信頼できる人たちとこれは本当におもしろいのか、吟味していく時間はとても長いです。
常日頃から、人の何百倍もこれは本当におもしろいのかと疑っています。今だったらまだ直せるって感じで、最後までちゃぶ台をひっくり返しながら作品を公開するギリギリまで考え続けています。
 野澤
野澤川村さんの作品づくりを継続させているモチベーションはどこにありますか?
 川村さん
川村さんよく他の人が作った映画を観て「おもしろい、悔しい」となったりするんですが、できれば「おもしろい、悔しい」と思わせる側でいたいですよね。たとえばポン・ジュノ監督の『パラサイト 半地下の家族』を観ていて「どうしてこういうことを思いつくんだろう!」ってびっくりして感動もするんですけど、なるべくそれはやっている側の方がいい。
 野澤
野澤川村さんは映画の仕事が始まる前は昔の映画をひたすら観る、と聞いたことがあるのですが、どのくらい観ますか?

 川村さん
川村さん一つの小説を書くのに100、200冊ぐらい本を参考資料として読むし、映画をこういうテーマで撮ろうと思ったら何百本と観るんですよ。『仕事。』という対談集で、初回に出てもらった山田洋次監督から「学ぶというのは、真似るということだよ」と教わったんです。「落語家でもなんでも一回モノマネして、モノマネできるようになったらオリジナルの技に挑戦する。個性っていうのはなんだかわからない。だから一回真似てみると、それでもはみ出しちゃうっていう部分が個性なんだよ」と聞いたい時に「なるほど」と思った。
最終回には坂本龍一さんが出てきて、「自分はたくさん音楽を聴いた」けど、「それはモノマネをするためじゃなくて、過去にないものを自分が作るために聴いたんだ」とおっしゃっていた。山田洋次監督と坂本龍一さんの言葉は実は対になっているんですけど、いいところはモノマネして自分がそれをアップデートできるかってところでもあるし、もうこれはやられているからやめようと確認するためでもあります。知らず知らずのうちに人のモノマネをしているっていうこともあるので、それをしないためにもたくさんの作品を観ます。
マーケティングは大事。でもマーケティング発想でものを作らない
 野澤
野澤香田さんは「売れるもの」をどうやって見つけているんですか?
 香田さん
香田さん最近、僕が大事だと考えているのは「マーケティングしなくていいのが最大のマーケティングだ」っていうこと。自分がユーザーとしていいかどうかわかるものは、一定の人には届けられる、というのが勝利のパターンだと思っていて。それがマーケットとして大きくなる場合もあれば、大きさはそうでもないことはあうんだけど、マーケティング、ターゲティングしなくてもいい、自分でいいということがわかる何かをやってみることが大事だなと。ザッカーバーグだって、同じハーバード大学の学生向けに作ったSNSが今のFacebookになったみたいなことだし。
自分の感覚でいいかどうかわからないターゲットを相手にものをつくると、怖くなって足し算ばかりして引き算ができなくなる。今はあれこれ継ぎ足したものより、ある特定のいいものだけに絞ったものにニーズがある時代。足し算ばかりしたものは、厳しいよね。
誰もがスルーする違和感や秘密に気づけるか?
 野澤
野澤最後の質問になります。これからクリエイティブやものづくりを仕事にしていきたいという学生さんは、何から始めていくのがいいと思いますか。大きく分けるとプロデューサー、マーケターなど作品を広げたり繋げる人か、それとも最初は書く、作るとか創作の根幹を担うのか。どちらの方がオススメですか?
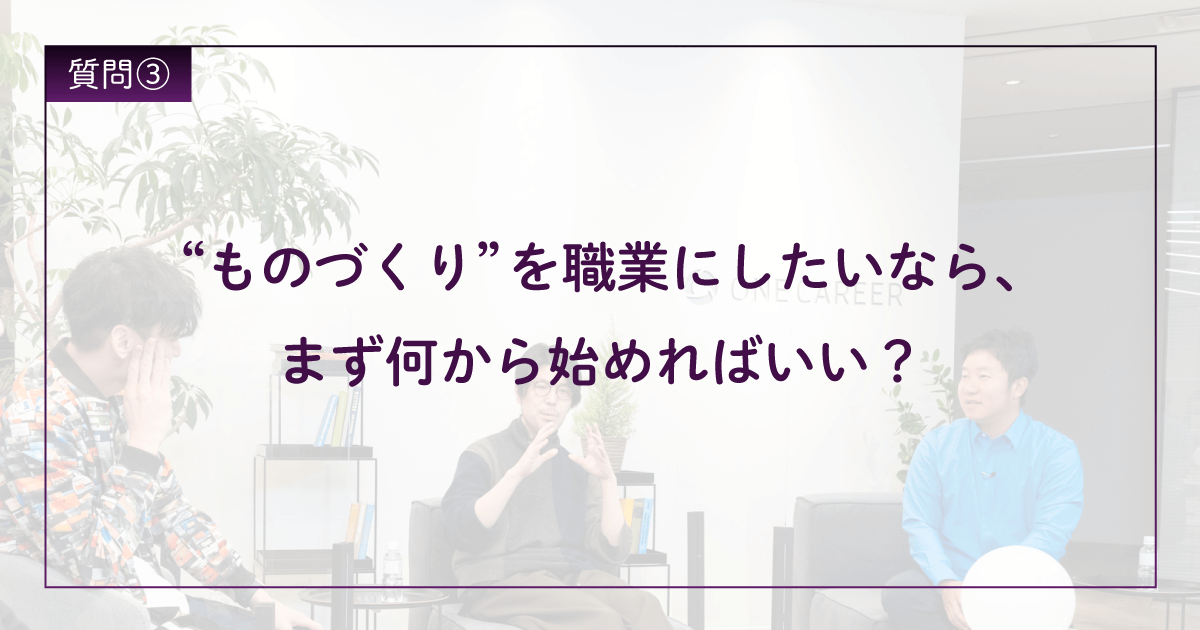
 川村さん
川村さんまずは自分がやりたいクリエイティブに、お金を使わないといけないと思うんです。よく、「映画作りたいです」という人に「今年、映画館で何を観た?」って聞くと「いや、ネットとかレンタルで」ってことが多いんですよね。「小説の編集やりたいんです」という人に「本屋で何の本を買った?」と聞くと、「いや、最近買ってないかも」とか。それではプロになれないと思うんですよね。やっぱりお金を使っておもしろかった時の喜びや、つまらなかった時の腹立たしい気持ちとか、そういう気持ちがわからないでプロ側に回りたいというのはちょっと無理があるんじゃないって思う。そうやってクリエイティブに支払われているお金で僕たちはものを作っているわけですし、クリエイターはそれで生きているから。
もう1個は、作る話になるとたとえば書く、読むなどテクニックの話になることが多い。だけど、テクニックは何年もやっていくことで身につくことでもあります。だから、何をどう作るかということよりも、何に“気づく”かという方が遥かに重要なんですよね。
僕は「ポストの上のクマ」の話をよくさせてもらうんです。
数年前、僕が使っていた駅の前にある郵便ポストの上にクマのぬいぐるみが置かれていたんです。「あれ、なんだこれ? 誰がこんなところに置いていったんだ?」と不思議に思って、電車を乗って仕事に行きました。2日目、駅に行くと、まだ置いてある。3日目、まだ置いてある。「なんなんだこれ。なんで誰も何も言わないんだ?」と思った時に“あること”に気づいたんです。
このクマのぬいぐるみは、駅を使う何千人という人が全員気づいているなと。気づいているけど、誰も何も言わない。その時に、そのクマのぬいぐるみを持ち上げて「これ誰のですか」って叫ぶのが僕の仕事だと気づいたのです。
まったく架空の物語を捕まえてくるんじゃなくて、みんながわかっている、みんなが気づいてる、みんな不満に思っている、けれどもなぜか言葉になっていないものを、言葉にする、物語にする、映像にする、音楽にする、っていうのが自分の仕事なんです。だから大事なのは“気づく”ことなんです。
そういうことはいっぱい転がっているんだけど、みんなスルーしているんです。だけど、それを表現したものが強烈な作品となっていく。実はそこら中にあるはずのヒントに気づくのがクリエイティブだと常々思っています。

 野澤
野澤お時間が来てしまいました。最後に一言だけもらえますでしょうか。
 香田さん
香田さん自分が今20代だったらどうしますかって、こんな難しい質問はないなって思うぐらい難しい。
そもそも答えはないし、選べる数じゃないし、逆に肩肘張って自分で選んだものを正解にすることも違うと思う。川村さんが話していた「これはやらない」というものを削っていって、残った中で自分の歩みを決めていくみたいなことができれば良いのかなと。今は風の時代とか言われていますけど、力が入りすぎていると方向転換ができないじゃないですか。人も、筋肉も、心も。だから柔らかく進んで、こっち側も行ってみるけどいつでも方向転換をしながら生きていけると考えれば、就職も人生も幸せに繋がっていくんじゃないかと、思っています。
 川村さん
川村さん今日ここで観て頂いている人の中で、将来アカツキに入る方もいるでしょう。もしかしたら映画業界や出版業界や音楽業界に来てくれる方もいるかもしれない。エンターテインメントの世界って狭いし繋がってるので、これから先、仕事でもし僕と会うことがあったら、「あのときイベントで観ていました」って声をかけてもらえると嬉しいなと思います。今日はどうもありがとうございました。
ゲスト紹介
川村 元気氏
映画プロデューサー・小説家
1979年生まれ。
『告白』『悪人』『モテキ』『おおかみこどもの雨と雪』『君の名は。』『怒り』『天気の子』などの映画を製作。12年、初小説『世界から猫が消えたなら』を発表。同作は世界22カ国で出版され、累計200万部を突破し、ハリウッドでの映画化も決定した。18年、佐藤雅彦らと製作した初監督作品『どちらを(英題:Duality)』 がカンヌ国際映画祭短編コンペティション部門に出品。著書として小説『億男』『四月になれば彼女は』『百花』対話集『仕事。 』『理系。 』『ブレスト』など。
初の翻訳を手がけた『ぼく モグラ キツネ 馬』が発売中。

この記事は2021年2月16日(火)に実施した特別企業説明会「ACE」をもとにしています。
文:池田 鉄平 写真:大本 賢児 デザイン:松本 奈津美 編集:鶴岡 優子



